ヒップホップ好きのスポーツ選手や文化人のキャリアについて全4回に渡ってインタビューしていく「あの人も実はヒップホップ」。今月は昨年初の著書『はじめての近現代短歌史』をリリースされた、歌人で文芸評論家の髙良真実(たから・まみ)さんにお話をお伺いしました。Vol.1の今回は歌人としての活動や短歌の世界について話して頂きました。
前回の記事はこちら→ 挫折から独立まで――徳谷柿次郎、二度の上京と挑戦の軌跡
ヒップホップ好き歌人・髙良真実とは?

レペゼン:
自己紹介をお願いします。
髙良真実:
歌人で文芸評論家をしている髙良真実(たから・まみ)と申します。出身は沖縄の那覇市です。去年まで歌人以外の仕事もしていたんですが、昨年会社を退職してからは、自分の本を書いたり、執筆依頼をいただいたり、あとは地元の歌壇の選者をさせてもらったりしています。ラップミュージックも中学生の頃から大好きで、特に沖縄のラッパーを中心に聴いていますね。
レペゼン:
ありがとうございます。ヒップホップ好きの歌人ということで、インタビューさせて頂くのを楽しみにしておりました。正直、私は短歌の世界のことはまったく知らない状態で髙良さんの著書『はじめての近現代短歌史』を拝読させて頂いたのですが、こんな世界があるんだとぶっ飛びました!ヒップホップのリリックの世界に負けず劣らず非常に刺激的な世界だなと。まず今回は「歌人」という職業がどういうものなのか教えて頂けますか?
【著書「はじめての近現代短歌史」】
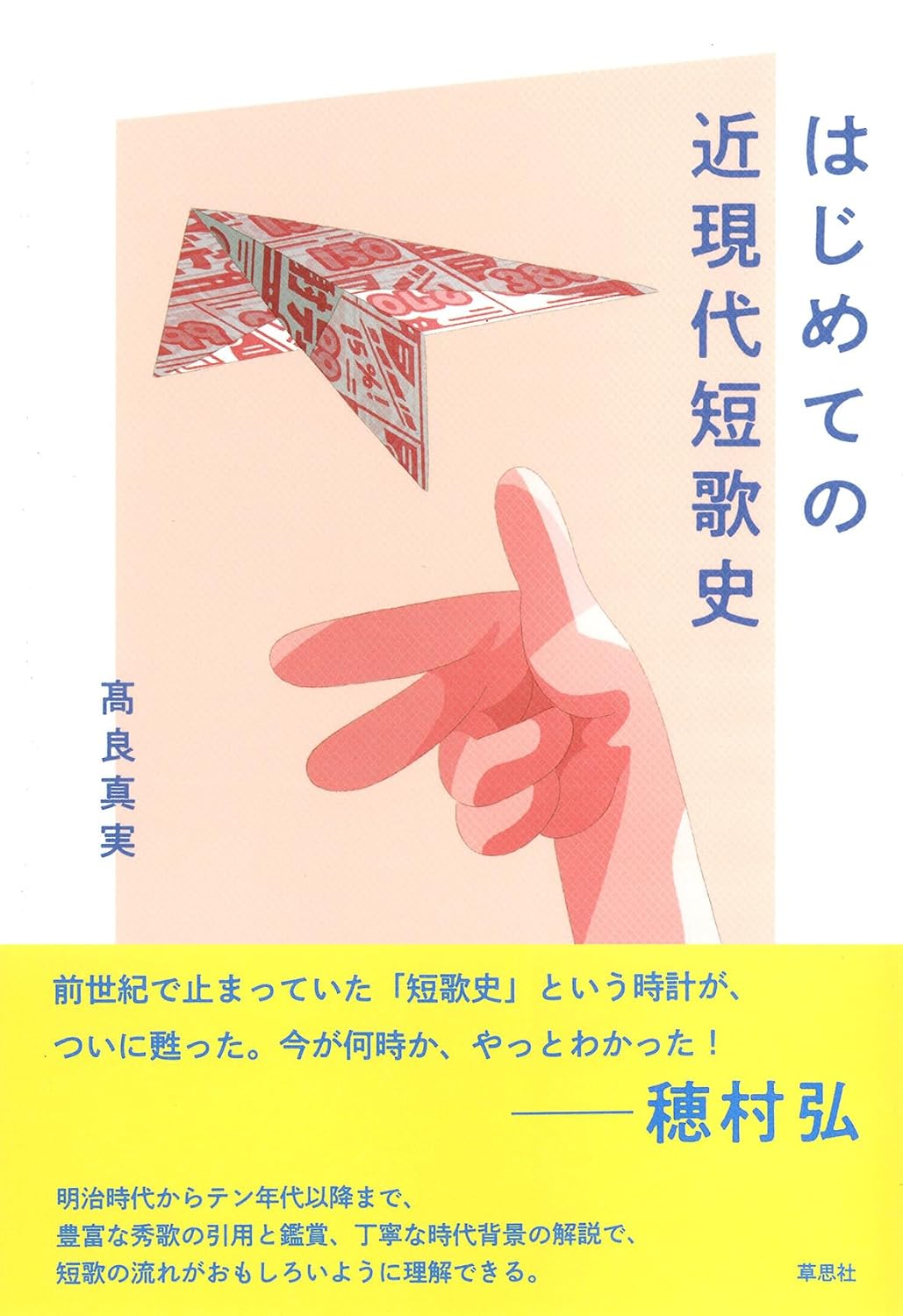
髙良真実:
まず短歌を作っている人を広い意味で「歌人」と呼びます。その中でも賞を取ったりして、本や歌集を出していたり、また講習をして生活してる人をプロ歌人とでも言えるのかなと。
レペゼン:
なるほど。そこはラッパーとかと同じ感じですね。
髙良真実:
そうですね。一応私はありがたいことに歌人としてお仕事を頂いて、生活しておりますので、いわゆるプロという捉え方になるのかなと思います。
レペゼン:
めちゃめちゃ興味深いです。まずそもそも「短歌」というものがいまいちわかってないのですが、俳句、川柳などとは何が違うのですか?
意外と知らない、短歌・俳句・川柳の違い
髙良真実:
短歌は「五・七・五・七・七」の形式の歌です。有名なものだと百人一首ですね。例えば「ちはやぶる・神代も聞かず・竜田川」までだと「五・七・五」ですが、短歌はこれに「からくれなゐに・水くくるとは」という「七・七」をつけるんです。
レペゼン:
ちょっと長いんですね。
髙良真実:
そうなんです。で、なぜ短歌と呼ぶかというと、実は短歌の以前の時代に「長歌(ちょうか)」というものがあったんです。これは短歌よりさらに長い形式で、「五・七・五・七……」と後にずっと歌を付け足すことができるんです。その長歌が簡略化されたものが、短歌なんです。
レペゼン:
「長歌」が短くなって「短歌」だったんですね!面白いです!
髙良真実:
そうなんです。ところがだんだんこの短歌の「五・七・五・七・七」のスタイルも長いぞと言われ出して。それで次は上の句と下の句を別の人が読むスタイルが生まれました。それを「連歌(れんが)」と言います。この連歌から上の句だけを取り出したのが「俳句」ですね。
レペゼン:
おぉぉ。
では俳句はかなり時代が下ってからのカルチャーなんですね?
髙良真実:
室町時代くらいですね。それがもっとカジュアルになっていったのが「川柳」なんです。
レペゼン:
なるほど。めちゃくちゃ面白いですね。
そんな歌人・髙良さんの生活が気になるんですが、普段はそれこそラッパーが曲を作るように、短歌の制作をされているんですか?
短歌界の“Def Jam”!?
歌会と短歌結社のリアル
髙良真実:
最近は本を書くことが多いです。『はじめての近現代短歌史』は初の書籍だったのですが、今はそれとは別の本の執筆もさせてもらっています。あと、自分の短歌に関しては「歌会(うたかい)」という会が開かれる時に作ります。
レペゼン:
歌会?なんですかそれは?
髙良真実:
まず10人くらいが自作の短歌を持ち寄って集まります。それを無記名で記入したものをシャッフルします。それを紙に印刷して配り、その中から自分が好きだと思う歌について話していく。そして最後に作者が明かされるという感じの遊びです。
レペゼン:
めっちゃおもしろいです。誰のリリックかわからない状態でジャッジするラップバトルみたいなものってことですよね?
髙良真実:
まぁそうかな笑
要は作者に対する忖度がないようにってことですね。もともと明治以前は「選者(せんじゃ)」と呼ばれるジャッジ的な立場の人に自分の短歌を提出して、その選者が認めた歌だけが選ばれ、吟味されるのを歌会と言ってたのですが、明治時代に歌人の正岡子規(まさおか・しき)が匿名で互いを批評しあうスタイルを持ちこんでからはそっちが主流になっていますね。
レペゼン:
髙良さんも歌会を主催されるんですか?
髙良真実:
私が開催することもありますが、「短歌結社」が開く場合も多いですね。
レペゼン:
「短歌結社」!?
なんですかそれは笑
髙良真実:
これも短歌特有の風習なんですけど、ヒップホップでいうとレーベルに近いものかもしれないです。文学的な志を同じくする人たちが結社を作るんです。私が入っているのは「竹柏会(ちくはくかい)」という現存する最も古い結社で。地域は特に関係ないんですが、同じ理念を共有しています。
レペゼン:
なんかカッコいいです。短歌会のDef Jam みたいな感じで。
その結社は全国にあるんですか?
髙良真実:
無名の結社も含めると数えきれないんですが、ある程度名前が通っている結社は10個くらいあります。例えば京都だと「塔短歌会(とうたんかかい)」というものがあったり。結社が掲げる先人の作品を読み込んだり、勉強会をしたりといった行動が、その結社ごとのカラーを作っています。
レペゼン:
まさにレーベルって感じですね。そんな短歌の世界で活躍されている高良さんはラップミュージックもお好きということで、最近ハマっているラップソングとかありますか?
短歌人も好きになる唾奇の魅力とは?
髙良真実:
最近はチルい曲が好きで。今年出た唾奇のアルバムの中の「NEKO」が好きです。『ジャム・ザ・ハウスネイル』というクレイアニメの主題歌の「猫が猫であるように 犬が犬であるように 全身全霊 僕でありたい」という歌詞がこの曲のフックにサンプリングされているんです。
【唾奇 – NEKO】
レペゼン:
NHKのEテレで放送されていたアニメですね!懐かしいです!
髙良真実:
そのアニメを見ていた幼少期の記憶をくすぐられて、沖縄時代を思い出すのかもしれません。「夕方くらいにあのアニメ見てたなあ」って。しみじみと良い曲だなと思いました。もちろん前後のバースも好きですが。
レペゼン:
特にどういった部分に惹かれますか?
髙良真実:
唾奇さんは若い頃の貧しかったことも赤裸々に歌われていますが、私も子どもの頃は、母子家庭で、経済的に苦しかった時があって。ボロボロのアパートに住んでいたのですが、そういったアンダークラス(長期的な貧困状態にある人々の階層)から成り上がっていくパターンって実は歌人には少ないんです。ただ唾奇さんのリリックからはそういうバイブスももらえる。そこも魅力かもしれませんね。
想像以上に奥深い短歌の世界。次回は髙良さんの沖縄時代、そしてヒップホップとの出会いについて聞いていくよ!お楽しみに!







